Security NEWS TOPに戻る
バックナンバー TOPに戻る
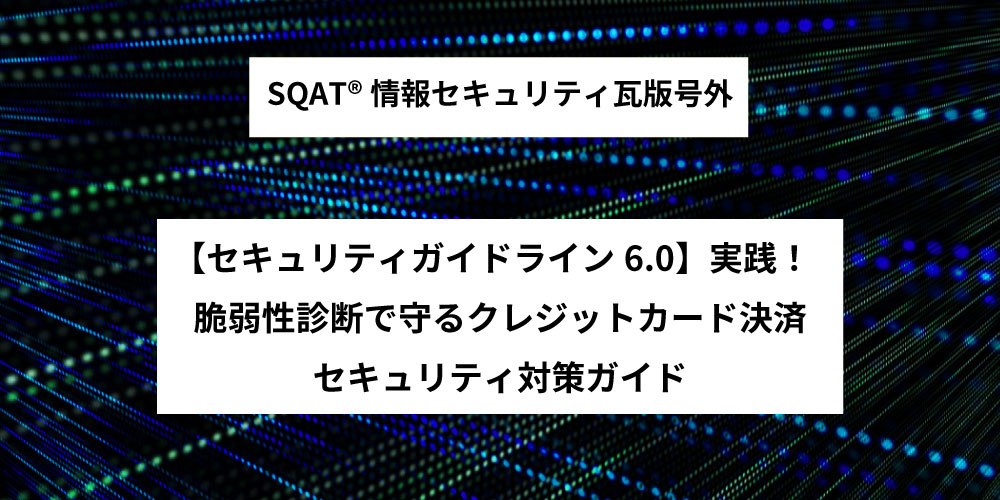
お問い合わせ
お問い合わせはこちらからお願いします。後ほど、担当者よりご連絡いたします。
はじめに
昨今、キャッシュレス化の推進とともにクレジットカード決済の利用が急増しています。日本では2025年6月までにキャッシュレス決済比率40%を目指す施策が進行中ですが、依然としてクレジットカード決済はキャッシュレス決済全体の約83.5%を占め、消費者や加盟店にとって非常に重要な決済手段です。しかし、その一方で情報漏えいや不正利用、特にECサイトなど非対面取引における不正利用被害は深刻な問題となっています。本記事では、「クレジットカード・セキュリティガイドライン【6.0版】」に基づく対策のうち、特に「脆弱性診断」の視点に着目し、決済システムやWebサイトにおけるリスクの検出とその対策の必要性、具体的な診断手法についてご紹介します。
【関連ウェビナー開催情報】
弊社では4月2日(水)13:00より、「今さら聞けない!PCI DSSで求められる脆弱性診断-いよいよ未来日付要件が有効に!PCI DSSv4.0での脆弱性診断実施におけるポイントとは-」と題したウェビナーを開催予定です。PCI DSSv4.0で求められる脆弱性診断・ペネトレーションテストについて今さら聞けない!?内容を徹底解説いたします。ご関心がおありでしたらぜひお申込みください。詳細はこちら。
クレジットカード決済の現状とセキュリティリスク
利用環境の変化とリスクの多様化
政府のキャッシュレス化推進施策により、決済手段が多様化する中、クレジットカードは依然として主要な決済手段です。一方、EC加盟店やMO・TO取扱加盟店では、Webサイトの設定不備や既知の脆弱性を悪用した第三者による不正アクセス、フィッシング攻撃によってカード情報が窃取される事例が相次いでいます。このような背景から、決済システムやWebサイトの脆弱性診断が不可欠となっており、早期にリスクを把握し対策を講じる必要があります。
ガイドラインの役割
「クレジットカード・セキュリティガイドライン【6.0版】」は2025年3月、クレジット取引セキュリティ対策協議会によって公開されたガイドラインで、PCI DSSをはじめ、割賦販売法などの法令に基づく実務上の指針や各種技術・運用対策をまとめたものです。その中では、EC加盟店のシステムおよびWebサイトに対して「脆弱性対策」を講じることが強調されており、脆弱性診断やペネトレーションテストの実施が推奨されています。
脆弱性診断の視点から見るセキュリティ対策の現状
脆弱性診断の目的
脆弱性診断は、以下の点でセキュリティ対策の強化に貢献します。
- 設定ミスや構成不備の検出
システム管理画面のアクセス制限やデータディレクトリの設定不備、ログイン試行回数制限の設定など、運用上の細かな不備を早期に発見。 - ソフトウェアやプラグインの脆弱性の把握
SQLインジェクションやクロスサイト・スクリプティングなど、Webアプリケーションの脆弱性診断を通じて、最新の攻撃手口に対応した対策が必要かどうかを判断。 - 実際の攻撃リスクの定量評価
ペネトレーションテストによって、実際に悪意ある攻撃者が侵入可能なポイントを実証し、リスクの深刻度を数値化することで、対応の優先順位を明確にします。
ガイドラインに基づく対策と脆弱性診断の連携
ガイドラインでは、EC加盟店に対して「脆弱性対策」の実施が求められています。具体的な対策例としては以下のようなものが挙げられます。
- システム管理画面のアクセス制限と多要素認証の導入
- データディレクトリの露見防止
- 定期的な脆弱性診断とペネトレーションテストの実施
- ウイルス対策ソフトの運用とシグネチャーの更新
これらの対策は、診断結果をもとに、PCI DSS 準拠のための必要な修正や改善措置として実施されます。さらに、ガイドライン内では、不正利用対策としてEMV 3-D セキュアの導入や、リスクベース認証(RBA)の精度向上など、動的な対応策も推奨されています。脆弱性診断の結果を踏まえた上で、システムの安全性を確保するための重要な要素となります。
具体的な脆弱性診断の手法と検査ポイント
システム管理とアクセス制御の検査
脆弱性診断で確認可能なポイント:管理画面ソフトウェアの既知脆弱性(例:古いバージョンの使用)や、デフォルトのパスワードが残っていないかなど、一般的なセキュリティ設定のチェックは脆弱性診断で検出できます。
Webアプリケーションの脆弱性診断
脆弱性診断で確認可能なポイント:SQLインジェクションやクロスサイト・スクリプティング(XSS)など、一般的なWebアプリケーション脆弱性は最新の診断ツールで検出可能です。ファイルアップロード機能における拡張子やファイルサイズの制限が設定されているかも、検証できます。
補足:Webサーバーやアプリケーション全体の構成評価は、脆弱性診断だけでなく、運用監査も併用することが望ましいです。
データディレクトリとサーバー設定の検査
脆弱性診断で確認可能なポイント:公開ディレクトリに重要なファイルが誤って配置されていないかをチェックできます。重要ファイルの配置状況や非公開設定の適切性は、詳細な設定レビューや管理者へのインタビューを通じての評価もしくはペネトレーションテストが必要な場合があります。
ウイルス対策とマルウェア検知の検査
脆弱性診断で確認可能なポイント:ウイルス対策ソフトのシグネチャー更新状況や、定期的なフルスキャンが自動ログから確認できる場合があります。
補足:実際の運用状況(更新頻度やスキャン実施の確実性)は、システム管理者への確認やログの監査が求められます。
委託先管理と情報共有の確認:外部委託先のセキュリティ状況や、PCI DSS準拠、ガイドラインに基づく対策の実施状況は、脆弱性診断では検出できません。委託先との契約内容、セキュリティポリシーの文書、定期監査の結果などを通じて確認する必要があります。
注 ) 上記の検査項目には、脆弱性診断で検出可能なものと、レビューや運用監査が必要なものが混在しています。脆弱性診断だけでは完全に評価できない項目については、管理者へのインタビューや設定ファイルのレビューなど、追加の確認が必要となります。
脆弱性診断を実施するメリットと成功事例
リスク低減と迅速な対応
定期的な脆弱性診断により、システムの設定不備や新たに発見された脆弱性を早期に把握でき、対策の優先順位を明確にできます。実際に、あるEC加盟店では、脆弱性診断の結果を受けてWebサイトの設定見直しとパッチ適用を迅速に実施した結果、不正アクセスによる情報漏えい事故を未然に防いだ事例があります。また前述の通り、脆弱性診断だけでは検出できない項目もあります。あわせてコンサルティングサービスなどによる監査を利用することで、より堅牢なシステムを構築することができます。
コンプライアンス遵守と信頼性向上
ガイドラインに沿った対策を実施することで、PCI DSSや関連法令に準拠し、顧客や取引先からの信頼を得られます。その一環として、脆弱性診断および定期監査は第三者機関による評価や認証取得にもつながり、企業のセキュリティ体制の信頼性を向上させます。
まとめ
クレジットカード決済におけるセキュリティは、企業の信頼性や消費者の安全な利用環境に直結する重要な課題です。クレジットカード・セキュリティガイドライン【6.0版】に示されている対策の中でも、脆弱性診断はシステムの現状を正確に把握し、迅速な対策を講じるための基盤となります。
定期的な脆弱性診断やペネトレーションテストを通じ、設定不備や最新の攻撃手法に対する脆弱性を検出し、必要な修正や改善措置を講じることで、不正利用被害のリスクを大幅に低減できるでしょう。また、診断結果をもとに、PCI DSSやガイドラインに沿った対策の実施が、企業のセキュリティレベル向上とコンプライアンス遵守に寄与するため、各企業や加盟店は今後も継続的に脆弱性診断を実施することが求められます。
BBSecでは
BBSecは、PCI SSC認定QSA(PCI DSS準拠の訪問審査を行う審査機関)です。準拠基準についての疑問や対応困難な状況があるといったような懸念・不安などは曖昧なままにせず、QSAにご相談いただくことをおすすめいたします。準拠に向けた適切な対応を検討するためのアドバイスや、事情に応じた柔軟な対応も可能です。
お問い合わせはこちら
※外部サイトにリンクします。
PCI DSS v4.0対応脆弱性診断サービス随時対応受付中!
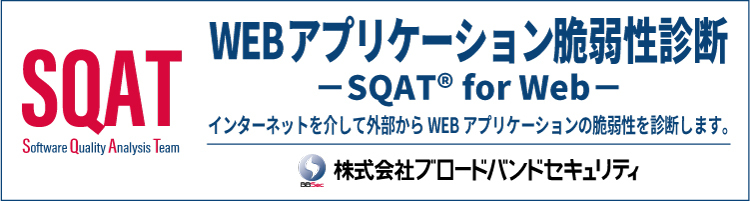
【※オプションサービス】脆弱性診断後対策支援サービス(VulCare)
組織が直面するサイバー脅威やリスクに対して、迅速かつ効果的に対応するための助言型サービスです。最短で1ヶ月~年間の期間にわたってセキュリティの継続的な改善とリスク低減を実現するために、専門家による分析と提案を活用し、常に最新の脅威に対応するためにご活用ください。
<サービス概要>
診断結果をもとに、セキュリティの専門家が具体的な対策方法の助言を行い、最適な改善策を提供します。短期的な緊急対応から、長期的なセキュリティ強化まで、貴社のニーズに応じた柔軟なサポートを展開し、脆弱性から組織を守ります。
お問い合わせはこちら
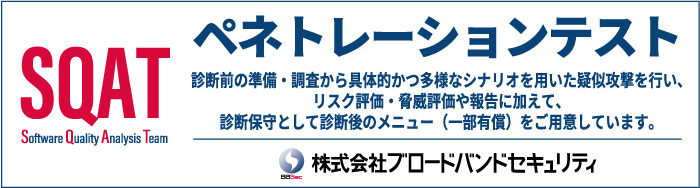
Security NEWS TOPに戻る
バックナンバー TOPに戻る
ウェビナー開催のお知らせ
「ランサムウェア攻撃の脅威~感染リスクを可視化する防御策の実践を紹介~」
「予防で差がつく!脆弱性診断の話~脆弱性による脅威とその対策~」
「知っておきたいIPA『情報セキュリティ10大脅威 2025』~セキュリティ診断による予防的コントロール~」
最新情報はこちら










