Security NEWS TOPに戻る
バックナンバー TOPに戻る

緊急事態宣言が解除されて1か月余り。通常勤務に戻る企業もあれば、テレワークを存続させる企業もあり、対応はさまざまです。不動産業界の調べによれば、東京都心のオフィスビルの空き室率は2020年3月以来微増しており、テレワークを今後も継続する企業は少なくないようです。
もともと欧州ではワークライフバランスの立場から在宅勤務(テレワーク)を推進してきました。オランダでは2016年に労働者が自宅を含む好きな場所で働く権利を認める法律が施行されています。フィンランドでも今年1月に同様の法律が施行されました。コロナ禍によってこうした動きは一層加速されており、米国は民間企業主体ではあるものの、やはり大手IT企業を中心に在宅勤務を義務化・恒久化する動きがあります。
しかしながら、日本においてはテレワークが欧米ほど浸透していません。国土交通省が今年3月に実施した「令和元年度テレワーク人口実態調査」では「会社でないと閲覧・参照できない資料やデータがあった」のは26.8%、また、セキュリティ対策に不安があったのは3.4%とありました。情報へのアクセス整備やセキュリティ対策不備に伴う漏えいへの不安がテレワーク推進の妨げになっていると考えられます。
テレワークにおける情報漏えいの不安

テレワークの場合、自宅での「在宅勤務」、出先や移動中に行う「モバイルワーク」、シェアオフィスなどを利用する「サテライトオフィス」のいずれにしても、インターネットを通じて業務データを社外で利用することに変わりありません。また、作業者が使用しているPCに重要なデータをダウンロードして作業する場合、セキュアゾーンで実施されないことも多いでしょう。そこにセキュリティ上の不安があるものと思われます。
総務省「テレワークセキュリティガイドライン第4版」においても、起こりうる事故として「情報漏えい」「重要情報の消失」を挙げています。確かに、企業が保有する設計図・製造ノウハウ・調査研究データなどの技術的な情報、取引内容・顧客リスト・財務データなどの営業上の情報は、事業存続および競争力強化にとって重要な情報資産であり、漏えいすることによるリスクははかりしれません。こうした懸念から、テレワークへの切り替えを躊躇する向きもあるでしょう。
そこで、適切にセキュリティを確保して情報流出の不安を解消しながらテレワークを実施できるよう、経済産業省は5月7日、「テレワーク時における秘密情報管理のポイント (Q&A解説)」を公表しています。以下に、そのポイントをみていきましょう。
「不正競争防止法」により保護される営業秘密(機密情報)
セキュリティ対策によって保護すべき、企業が保持する「営業秘密」は、一定の要件を満たすことで不正競争防止法の下で保護されます。法的保護を受けることにより、例えば電子データで取り扱われている機密情報がセキュリティの脆弱性を突かれて漏洩した場合でも、差止請求や損害賠償請求などが可能です。このため、事業における金銭的被害や信用失墜といったリスクを軽減できます。
ただし、営業秘密として法的に認められるためには、対象となるデータに対して以下の条件が整っていることが必要です。
1.秘密管理性:その情報が秘密であるとわかるように管理されていること
2.有用性:事業活動に役立つ情報であること
3.非公知性:世間一般に知られていないこと
「秘密管理性」の趣旨は、「企業が秘密として管理しようとする対象(情報の範囲)が、従業員等に対して明確化されることによって、従業員等の予見可能性、ひいては経済活動の安定性を確保する」ことにあるとされています。つまり、情報が営業秘密として保護されるためには、「秘密である」こと自体をはっきり示す必要があります。
「非公知性」は、営業秘密保有者の管理下以外では一般的に入手することができない状態とされています。このため、営業秘密としての条件を満たすには、容易に人に見られたり、聞かれたりしないようにしなければなりません。
テレワーク環境で営業秘密を保護する対策
テレワーク環境下で、秘密管理性と非公知性の要件を満たして情報を保護しつつ、情報漏えいを防止するには、状況に応じて以下のような対策が挙げられます。
| 状況別 | 対策の例 |
|---|---|
| テレワーク対応導入の第一歩 | ●営業秘密管理規程、情報取扱規定等をテレワークに即した内容に改訂 ●諸規程の従業員に対する周知徹底 ●情報に応じたアクセス権者の設定 等 |
| 業務における情報持ち出しおよび 社外からのアクセス | ●データのファイル名や当該データ上に「㊙」(マル秘)・「社内限り」等の秘密であることの表示を付す*1 ●情報のコピー・持ち出しにおける上長等の事前許可/返却・破棄ルールの周知・徹底と持ち出し記録の整備 ●紙の資料・PC等を机上等に放置しないといった取扱いルールの徹底 ●ID・パスワードによるアクセス制限の実施 ●チャットツールで営業秘密についてやりとりするスレッドと参加者を限定 等 |
| 社外作業 | ●PCにのぞき見防止フィルム等貼付の徹底 ●音声が漏れない場所でのオンライン会議実施徹底 ●公共無線LANの使用禁止、従業員のポケットWi-Fi・テザリングの禁止、業務使用Wi-Fiの貸与 等 |
| 情報漏えい、不正持ち出しの防止 | ●メールの転送・添付制限、送信前の上長承認、上長のCC追加設定 ●遠隔操作でPC内データを削除できるツールの利用 ●PCに対するUSB、スマホ接続不可設定 コピーガード付き記録媒体の利用 等 |
営業秘密として秘密管理性要件を満たすと認められる技術的要素

テレワークにおける情報流出対策として規程を整備し、徹底した従業員教育を行ったとしても、所詮は人間が実施することであるため、悪意の有無にかかわらず、すべてが絶対確実に守られるとは言い切れません。そのため、前述の対策の例にも、技術的に強制するような仕組みがいくつか含まれています。
●アクセス制御と権限管理の徹底
データ管理における秘密管理性要件については、通常、アクセス制御が実施されていることをもって、「秘密である」ことを示すと見なされています。これは、アクセス制御の基本的な考え方が、当該情報を知るべき者だけが情報にアクセス可能であるべきという「Need to Know」の原則に基づいていることと関係があります。アクセス制御とは、正規に承認されたユーザにのみコンテンツへのアクセスを許可するセキュリティ対策だからです。
このため、秘密管理性の要件を満たすためには、アクセス制御自体が適正に実施されている必要があります。例えば、同じアカウントを複数の従業員が使い回しているような状態や、パスワードに社員番号をそのまま当てはめていて他人が容易に推測可能な状況の場合、秘密管理措置を講じていないと判断される恐れがあります。
アクセス制御が「対象へのアクセスそのものを制御する」のに対し、「行為の実行権限を管理する」のが権限管理です。権限管理とは、ログインによってWebシステムやファイルサーバへアクセスするためのユーザを認証するシステムにおいて、各ユーザアカウントの役割を定義し、データに対する閲覧・編集等、実行できる処理についての権限を付与・管理することを言い、当該ユーザに対して必要最低限の権限を付与する「最小権限の原則(Least Privilege)」を適用します。データの重要性や種類に応じて、特定のグループだけが編集権限を持ち、他の従業員には閲覧のみを許可するといった設定です。
適正なアクセス制御・権限管理のどちらが欠けても「脆弱なシステム」であると言わざるを得ません。
●認証機構の堅牢化
アクセス制御に欠かせない認証機構ですが、IDとパスワードによる単要素認証は、リスト型ハッキング攻撃等の標的となりやすいため、テレワーク導入・継続に備え、パスワード強度に対するポリシーの見直しをお勧めします。現在、セキュリティの各種基準・仕様においては8文字未満のパスワードは脆弱であるとみなされており、14文字以上のパスワードが推奨されています。流出したパスワードや汎用的で推測容易なパスワードを排除する実装の導入も有効です。
しかしながら、ユーザにとっては長いパスワードを複数覚えておくのは至難の業であるため、パスワードの使いまわしもなくならないでしょう。これを防ぐには、ID/パスワード以外に、認証要素(指紋や顔等の生体認証、またはワンタイムパスワードトークンやSMS等の所有物認証)を1つ以上追加した、多要素認証の導入をお勧めします。
この他、データの管理についても注意が必要です。データをUSBやDVDに記録できないようにする、プロジェクト終了後のデータ消去について確認する手段を講じるなどです。
テレワーク導入・継続における技術的要素について、詳しくはこちらもご参照ください
法的要件の確認にも有効なセキュリティ診断
営業秘密として保護されるべき法的要件を技術的な側面で満たしているかどうか確認する有効な手段に、セキュリティ診断があります。営業秘密に当たる情報を扱っているWebアプリケーション、ネットワーク(プラットフォーム)、スマホアプリ、IoT機器等に対し、第三者であるセキュリティ専門企業による診断を受けることをお勧めします。
先に述べた、アクセス制御や権限管理が適切に導入・運用されているかも、セキュリティ診断によって確認できます。
自らは気づいていない脆弱性を洗い出して悪用された場合のインパクトを事前に調査し、技術的に対応できること、対応が難しければ法的保護を受けるために講じるべき回避策や代替手段として何を整備しておくべきかを検討するなど、リスク対応策を検討しておくことが事業継続の肝となります。
参考情報
・テレワーク時における秘密情報管理のポイント (Q&A解説)
https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/teleworkqa_20200507.pdf
・逐条解説 不正競争防止法
https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/20190701Chikujyou.pdf
まとめ
・テレワークは緊急事態宣言後も一定の割合で継続される見込み
・テレワーク導入・継続における情報流出の不安には、経済産業省による「テレワーク時における 秘密情報管理のポイント (Q&A解説)」が対策のヒントになる
・テレワーク環境下でも、会社の重要情報を「不正競争防止法」による法的保護の対象である「営業秘密」として管理することが肝要
・適正なアクセス制御と権限管理は営業秘密の秘密管理性要件を満たす技術的なセキュリティ対策である
・機密情報を扱うシステムに対するセキュリティ診断の実施は、リスク対策における技術的な対応策と法的保護策の切り分けにも活用できる
関連情報
●<インタビュー>上野 宣 氏 / ScanNetSecurity 編集長
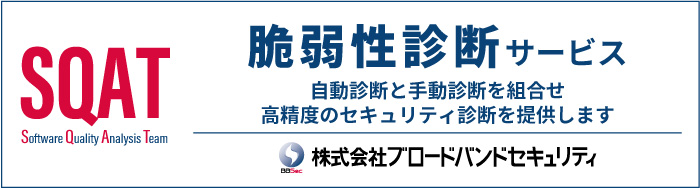
Security NEWS TOPに戻る
バックナンバー TOPに戻る






