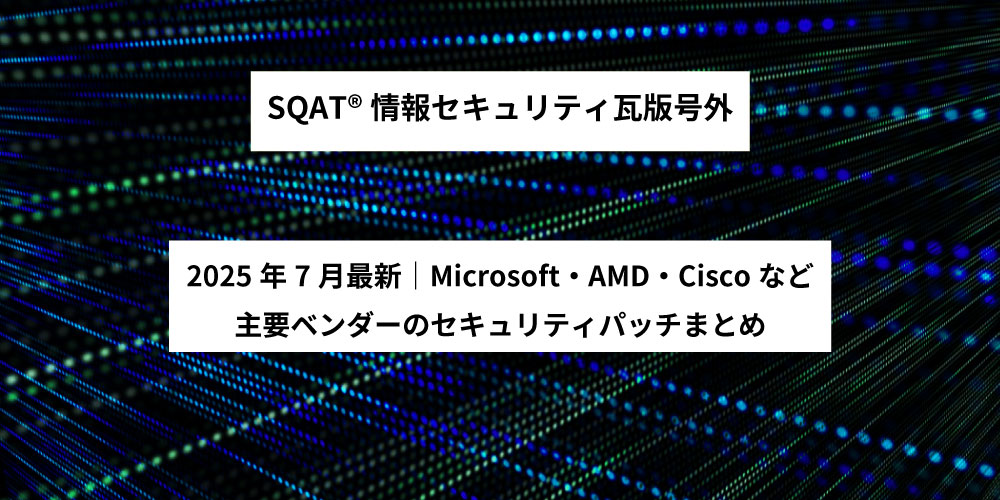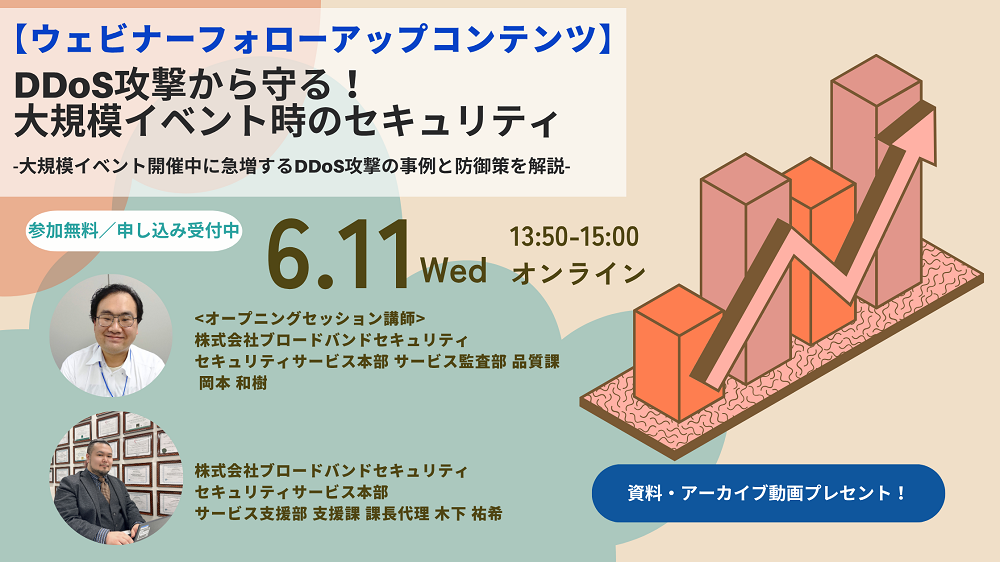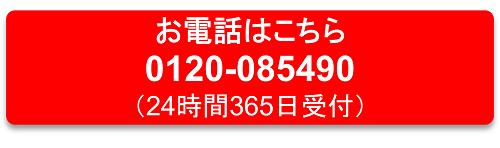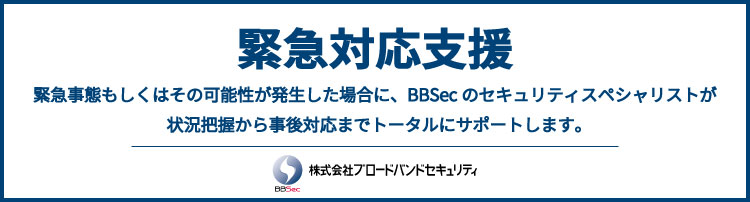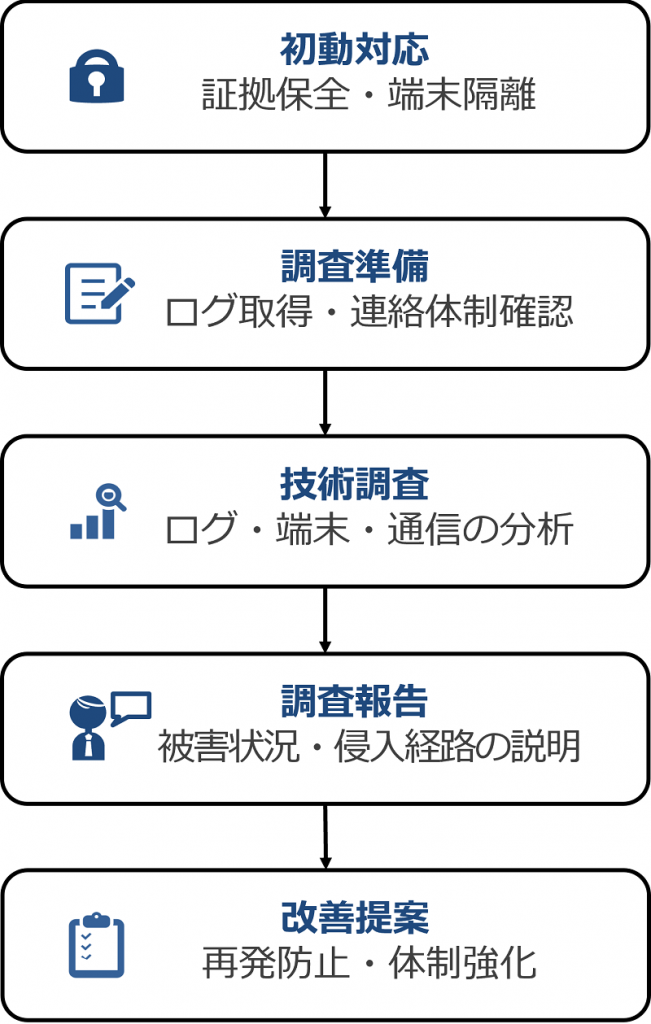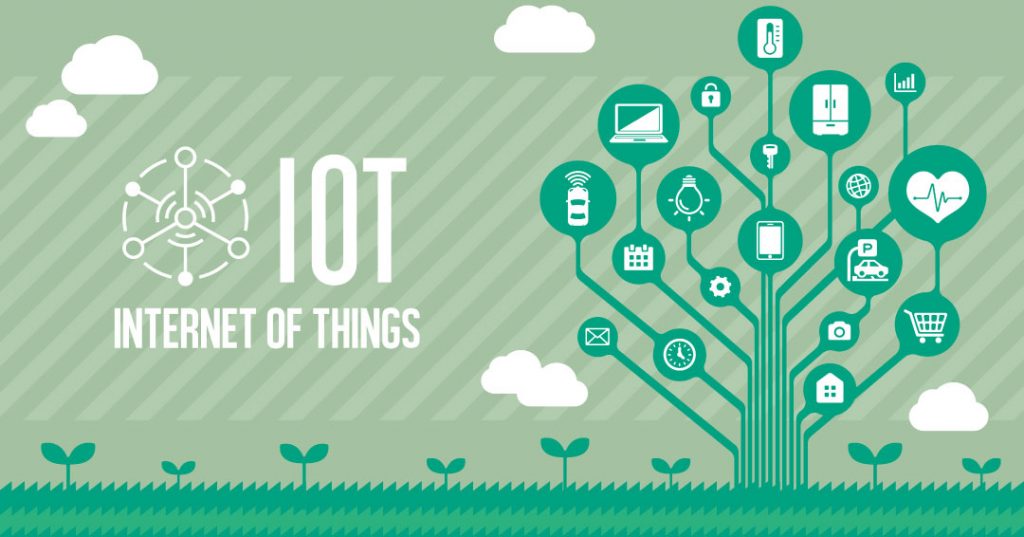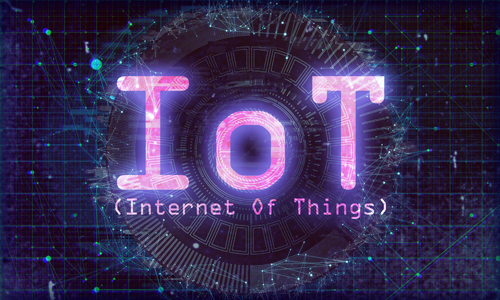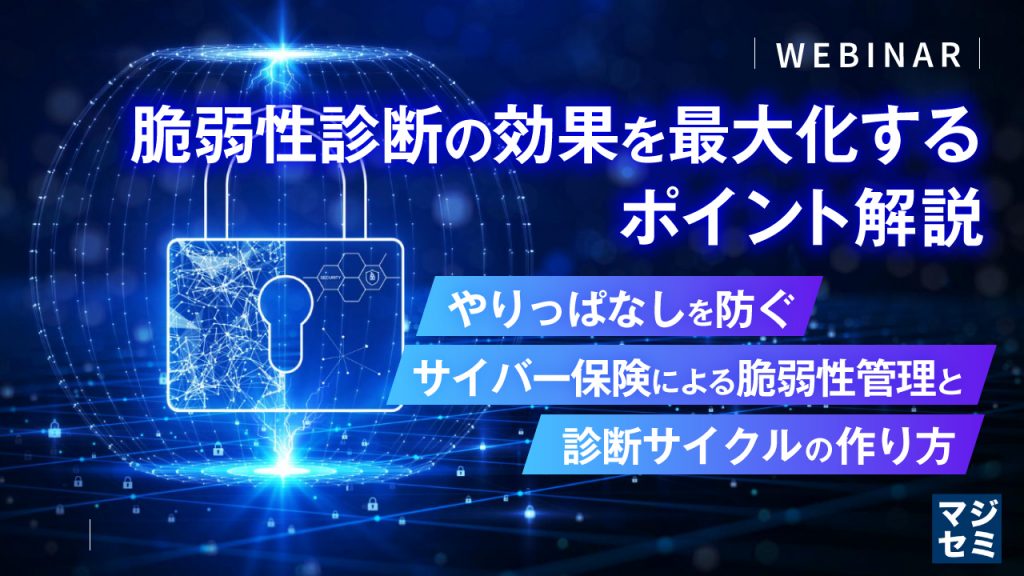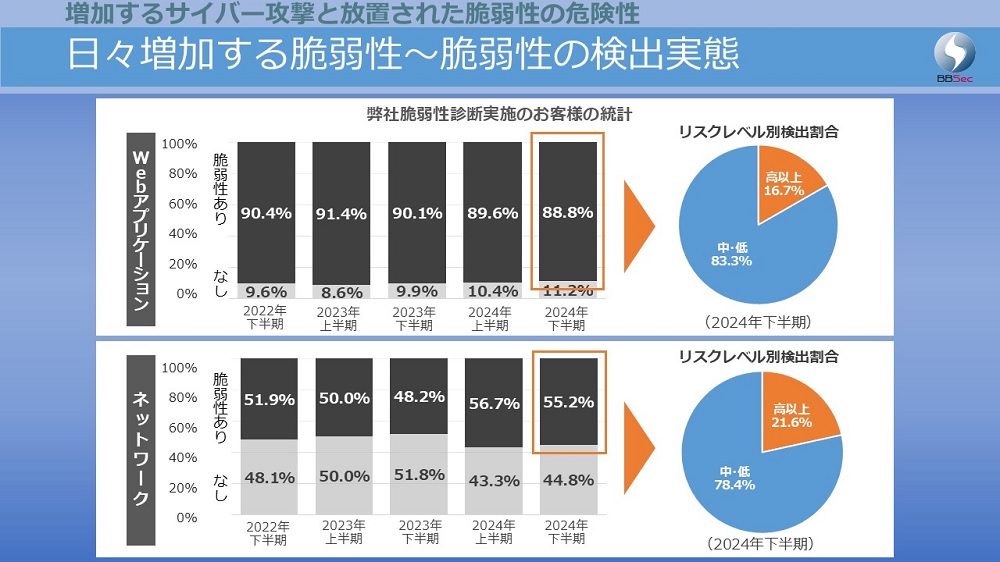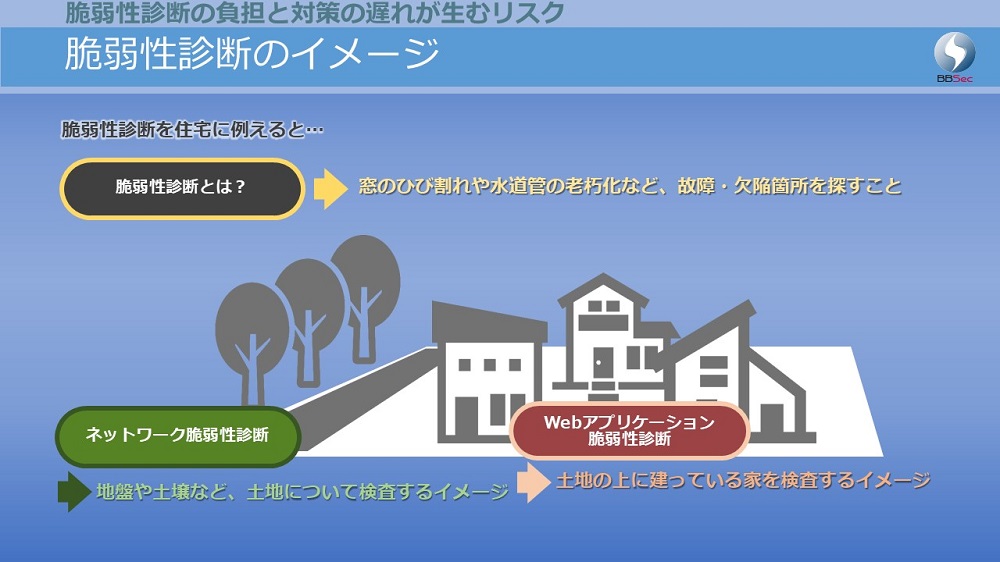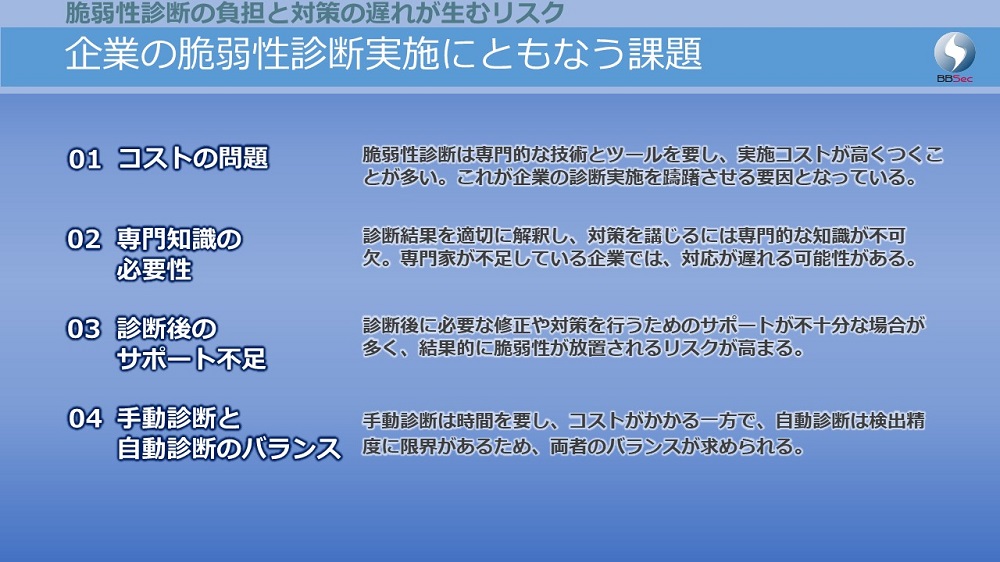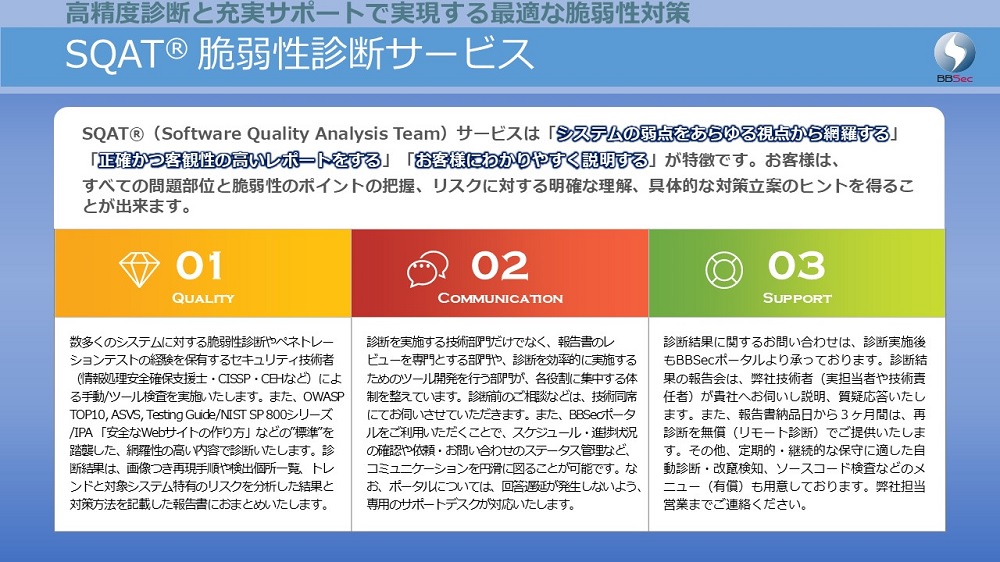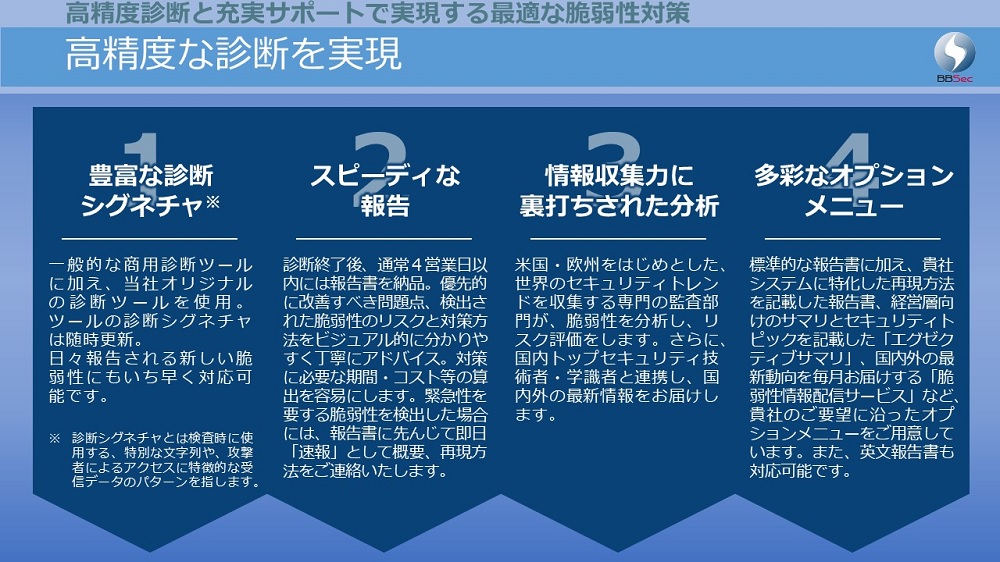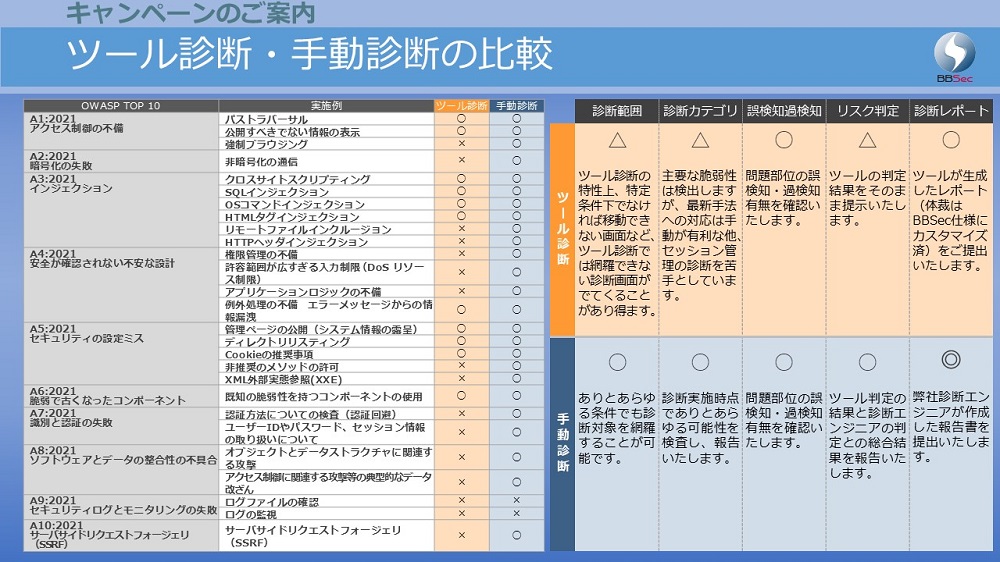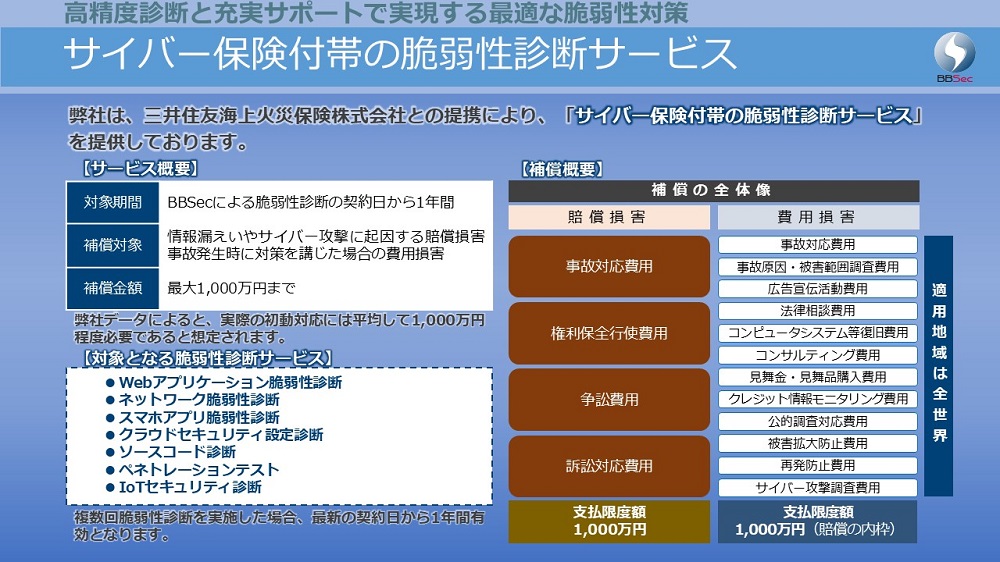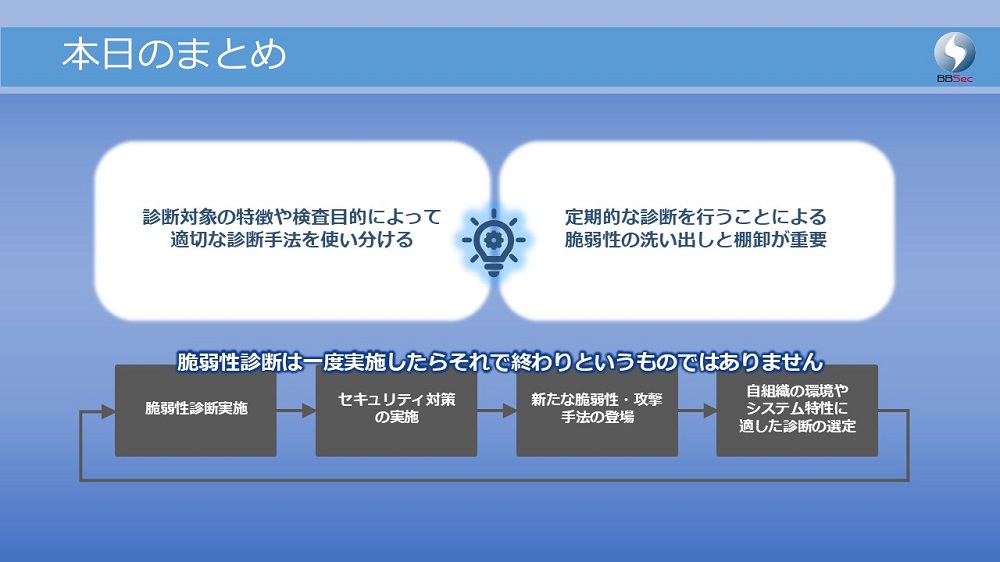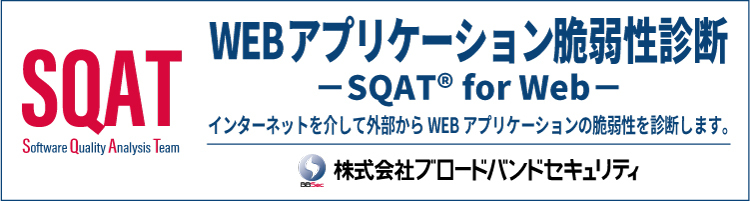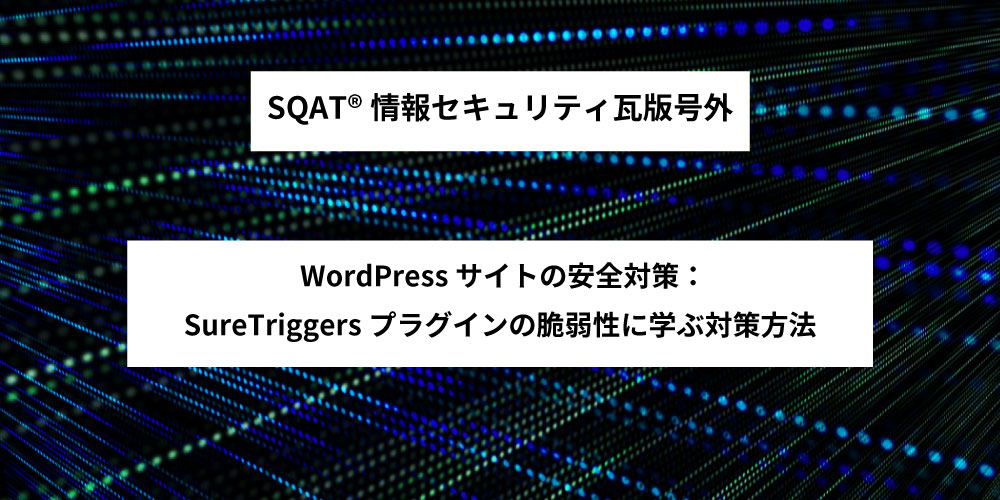| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-49719 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-49704 |
| https://www.amd.com/en/resources/product-security/bulletin/amd-sb-7029.html |
| https://www.microsoft.com/en-us/research/publication/enter-exit-page-fault-leak-testing-isolation-boundaries-for-microarchitectural-leaks/ |
| https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/publicationListing.x |
| https://www.fortiguard.com/psirt |
| https://source.android.com/docs/security/bulletin/2025-06-01 |
| https://source.android.com/docs/security/bulletin/2025-07-01 |
| https://www.ivanti.com/blog/july-security-update-2025 |
| https://support.sap.com/en/my-support/knowledge-base/security-notes-news/july-2025.html |
| https://www.cve.org/CVERecord?id=CVE-2025-30012 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-36357 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-36350 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-47988 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-49690 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-48816 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-49675 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-49677 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-49694 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-49693 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-47178 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-49732 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-49742 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-49744 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-49687 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-47991 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-47972 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-48806 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-48805 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-47994 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-49697 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-49695 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-49696 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-49699 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-49702 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-48812 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-49711 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-49705 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-49701 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-49706 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-49703 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-49698 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-49700 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-47993 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-49738 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-49731 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-49737 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-49730 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-49685 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-49756 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-48817 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-33054 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-48822 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-47999 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-48002 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-21195 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-49718 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-49717 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-49684 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-47986 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-47971 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-49689 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-49683 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-47973 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-49739 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-27614 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-27613 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-46334 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-46835 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-48384 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-48386 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-48385 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-49714 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-49661 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-48820 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-48818 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-48001 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-48804 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-48003 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-48800 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-48000 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-49724 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-47987 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-48823 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-47985 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-49660 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-49721 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-47984 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-47980 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-49735 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-47978 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-49666 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-26636 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-48809 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-48808 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-47996 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-49682 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-49691 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-49716 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-49726 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-49725 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-49678 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-49680 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-49722 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-48814 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-49688 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-49676 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-49672 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-49670 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-49671 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-49753 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-49729 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-49673 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-49674 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-49669 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-49663 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-49668 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-49681 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-49657 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-47998 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-48824 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-48810 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-49679 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-49740 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-48802 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-47981 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-47976 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-47975 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-48815 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-49723 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-49760 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-47982 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-49686 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-49658 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-49659 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-48821 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-48819 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-48799 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-49664 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-47159 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-48811 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-48803 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-49727 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-49733 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-49667 |
| https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/advisory/CVE-2025-49665 |